中小企業診断士は独学だと無理?試験が難しいと言われる背景
中小企業診断士資格は、取得すれば収入やキャリアアップに大きなメリットが期待できる人気資格である。最近では「ビジネスマンが取得を目指す資格ランキング」で1位に選ばれることもあり、世間での認知度も高くなってきている注目資格だ。
とはいえ、この資格は難易度が高いと世間一般では表現されるケースが多い。その難易度の高さから途中で挫折する受験生や数年かけても合格できないケースも少なくないのが実情だ。
だからこそ、「中小企業診断士は独学では難しい。予備校や通信講座が必要だ。」と言われることもある。
今回はその「中小企業診断士は独学だと合格することが無理なのか?」をデータも踏まえて解説していきたい。
まずは、中小企業診断士は独学だと合格できないと言われている理由を見ていく。
試験科目は7科目と幅広く、学習範囲が膨大であり、独学では効率的な学習ができず勉強時間が膨大になる可能性がある
まず、前提として中小企業診断士には、下記4つの試験と補修を乗り越えなければなれない。
一次試験(選択式)
二次試験(記述式)
口述試験
実務補修
まず一次試験は、選択式のマークシートで7科目もある。経済学・財務会計・企業経営理論・運営管理・経営法務・経営情報システム・中小企業経営政策で構成され、経営全般の知識を総合的に問われる。
合格基準は総得点の60%以上かつ、1科目でも満点の40%未満がないこと。一次試験は全7科目であるため、総得点が420点以上(700点満点中)で、かつどの科目も40点以上であれば合格となる。
つまり、1科目でも40点に届かなければ、即アウト。得意な科目だけで逃げ切る、という戦略は通用しない。得意科目・不得意科目はあるにしても最低限得点しなければいけない基準は設定されているということだ。
次に二次試験。中小企業診断士試験の二次試験は記述式の試験であり、一次試験の選択式と比較するとさらに難易度が上がると言われている。
知識を並べるだけじゃダメで、「じゃあ実際どうする?」みたいな実務的な考え方や、相手に伝わる文章力が問われる。問題の意図を外せば高得点はまず取れない。一次試験でどれだけ点を取っても、ここでつまずく人は本当に多い印象だ。
最後の口述試験は、落ちる人は少ないとはいえ油断は禁物である。二次試験の事例について突っ込まれるので、自分の答えをちゃんと振り返っておく必要がある。
要するに中小企業診断士試験は、知識だけじゃなく考える力や表現力までしっかり見られる。だからこそ合格するにはそれなりの勉強量が必要である。
この勉強量が膨大になるというのが、中小企業診断士試験の独学が無理だと言われる1つの要因である。勉強する範囲が多岐に渡り、勉強時間も膨大になる試験であるため、効率的な勉強計画が必要不可欠になる。
しかし、独学では「効率的な勉強の仕方」を最初から実践することは難しいと言える。もちろん、インターネットで検索すれば学習戦略は出てくる。
しかし、具体的にどの科目のどこをどれくらいの時間をかけて勉強すべきか?ということを体系的に説明しているサイトはほぼない。
これは予備校や通信講座がノウハウとして蓄積している分野。
独学と予備校・通信講座を比較すると、効率性の観点でいうと後者に軍配が上がるのは間違いないだろう。
年1回の試験で失敗するとリスクが大きい
上記で挙げた理由に関連するところではあるが、中小企業診断士試験の実施回数も独学が無理だと言われる理由の一つになっている。
中小企業診断士試験は1年に1度しか実施されないため、一度でも試験に落ちてしまうと、長期戦になることが確定する。
仮に、一次試験に落ちてしまうと次のチャレンジは1年後。一次試験に合格しても、二次試験に落ちると次のチャレンジは1年後。というように、1年に1度の試験のため一度の不合格で、合格までの期間が最低でも1年延長されることは間違いない
ちなみにストレート合格する率は5%ほどと言われている。これを聞くだけでも試験自体の難易度が高いことがわかる。
つまり、独学をして効率的な勉強ができないとかなり長期的な学習が必要になる可能性がある。こうなってしまうと、モチベーション維持が難しくなる可能性が高くなる。モチベーションが保てないと、勉強の継続ができなくなり、身につけた知識がどんどん忘れ去られていき、勉強の軌道を戻すことがかなり難しくなる。
中小企業診断士試験のモチベーション維持に関する詳しい話は下記を参照いただきたい。
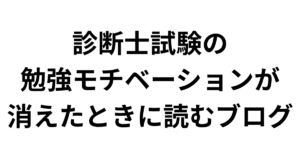
データで見る中小企業診断士の合格率
独学が難しい道であることはご理解いただけたと思う。ここからは、そもそもの中小企業診断士の合格率を見てみたいと思う。
ここではわかりやすいように年齢別で合格率を見てみる。
| 年齢・年代別合格率 | 2023年度(令和5年) | 2022年度(令和4年) | 2021年度(令和3年) | 2020年度(令和2年) | 2019年度(令和元年) |
| 20歳未満 | 12.14% | 6.62% | 13.33% | 12.67% | 5.56% |
| 20~29 | 21.34% | 20.89% | 23.08% | 24.82% | 17.15% |
| 30~39 | 22.72% | 22.43% | 24.88% | 26.27% | 21.75% |
| 40~49 | 20.84% | 19.81% | 23.54% | 24.09% | 21.78% |
| 50~59 | 20.80% | 18.87% | 24.08% | 24.72% | 22.34% |
| 60~69 | 19.74% | 16.88% | 23.72% | 23.28% | 20.92% |
| 70歳以上 | 12.10% | 13.99% | 11.81% | 16.53% | 14.60% |
| 合計 | 21.25% | 20.26% | 23.84% | 24.82% | 21.00% |
これをみると、年によってばらつきはあるが全体の合格率は20%前後であるといえる。高いような低いようなよく分からないと感じた方もいらっしゃると思うが、中小企業診断士試験は年に1度しか試験が実施されない。つまり、多年度受験生も一定数存在するということである。数年間勉強している人も含めてこの合格率ということは難易度はそこそこ高いと言えるだろう。
一方で40代・50代は実務経験が豊富ということもあり、中小企業診断士試験の基礎となる知識は既に持っている可能性がある。この場合は20代・30代よりもスタートダッシュは切りやすい。
ただし、あくまで”率”であるため、受験者数と合格者数の実数が知りたい方は下記のサイトを参照してほしい。
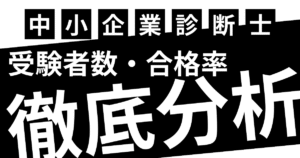
中小企業診断士の独学が無理だと思われる3つの理由
前述したように、最低でも1年間勉強し続けなければならない。もちろん、半年で合格できる強者も存在するのも確かだが、一般の人は1年以上しっかり学習しなければならないはずだ。
となると、1年以上継続的にモチベーションを維持し続け、学習を続けるのは非常にハードルが高いと言わざるを得ない。
長期戦の試験になること自体がモチベーションの低下を引き起こす一つの要因なのだが、他にもモチベーションを低下させる要因は大きく分けて3つある。
苦手科目を克服できず挫折する
中小企業診断士は合計で7科目に合格しなければならない。その試験範囲は幅広く、どうしても自分が苦手とする分野が出てくる。
その苦手分野の中には何度解説を読んでも理解できなかったり、なぜだか覚えることのできない内容が必ずと言っていいほど出現する。
こうなると真面目な人ほど、挫折してしまいがち。
予備校に通っていれば、勉強のカリキュラムがあり、最新の情報をもとに学習すべきポイントが理解しやすく、問題の添削や解説も質問できるけれど、独学ではそれができない。
これが中小企業診断士の独学が無理と言われる一つの要因である。
理解しても忘れてしまい定着しない
中小企業診断士試験は合計7科目で構成されており、1日で全てを勉強しながら合格を目指すのは非現実的。特に日中は働いている社会人の方の受験が多い試験でもあるため、どれだけ頑張っても1日に勉強できるのは1科目から2科目くらい。
しかし、7科目を順番に学習していく中で、最初の方に学習した内容は自分でもびっくりするくらい頭から抜け落ちていることがほぼ確実に発生する。
あの時は理解したはずなのに、、、また振り出しに戻った、、、という経験を必ず経験する。
幅広い試験範囲なのだから当たり前といえば当たり前なのだが、忘れてしまっている事実に直面するたびにモチベーションは削られていく。
私生活との両立が難しく学習が続かない
中小企業診断士試験だけを勉強し続ける生活なら合格は簡単かもしれない。しかし、多くの場合私生活との両立が前提となるだろう。
友達との付き合い、彼氏彼女との付き合い、家族とのイベント、自分の趣味、仕事に関する資格や試験の勉強、などなど。上げ始めたらキリがないくらい私生活のイベントは盛り沢山のはず。
そしてその多くが、楽しいことばかりだと思う。
こうなってしまうと、勉強を継続することが難しくなり、ついつい私生活のイベントの優先順位が高くなってしまうことがある。
これ自体は全く悪いことではないのだけれど、勉強しなかった期間が長ければ長いほど勉強内容は頭から消え去っていくのもまた事実。
こうなってしまうと学習効率はどんどん落ちていき、合格までの年数が多くなり、いつの間にかモチベーションが消え去る、、、ということが起きてしまう。
体験談からわかる、独学の落とし穴と成功の分岐点
独学で失敗する人の共通点
これは間違いなく、「モチベーションの維持ができずに、継続的な学習ができない人」である。
しかし、そもそも常にモチベーションを維持し続けて、継続的な学習が1年以上できる方は、「独学で中小企業診断士に合格できるか」なんて考える前に勉強を始めて勉強をしているはず。
ということは、この共通点を持っている場合がほとんどということである。
ただし、だからといって「独学が不可能」と言っているわけでない。むしろ独学に挑戦してみるもありだと思う。なぜなら、中小企業診断士に合格しても勉強は続く。吸収しなければいけない情報は試験範囲よりも膨大になる。ということはどのみち独学をする力は身につけておかなければいけない。
とあるとだ。中小企業診断士に合格するということと、独学の力を身につけることを一緒にやってしまうのは選択肢としてはありだと思う。
独学で成功した人が実践していた工夫
中小企業診断士を独学で目指すメリット・デメリット
独学のメリット
1. 費用を大幅に抑えられる
独学最大のメリットは、何といっても費用の安さ。
予備校や通信講座を利用すれば数十万円の費用がかかりますが、独学であれば市販のテキストや過去問集の購入だけで済み、数万円以内に抑えることも可能。しかし、これはあくまで「お金」にだけフォーカスした話。勉強の質や効率に目を向けると独学よりも予備校や通信講座を使った方が圧倒的に効率的で質も高いとはず。つまり、中小企業診断士試験にかけるお金だけではなく、時間まで費用としてみて比較することが重要であるといえそうだ。
2. 自分のペースで学習できる
独学なら、勉強をどのように進めるのかは自分でコントロールできる。仕事や家庭の事情で決まった時間を確保するのが難しい人にとって、好きな時間に好きな分量を進められるのは大きな利点。
3. 主体的に知識が定着する
中小企業診断士を独学で行うことの1番のメリットは多分これ。誰かに与えられたカリキュラムではなく、自分で調べ、考え、計画する過程そのものが学びになる。仮に中小企業診断士に合格したとしても、その後の中小企業診断士に関わる業務の中で勉強は必須。学び続けなければならない。
そう考えたときに、中小企業診断士に合格した後の勉強のコツを身につける意味であえて独学を選ぶのは一つの戦略である。
合格して終わりではなく、中小企業診断士試験の勉強を土台として未来につなげる勉強癖をつけるのは非常におすすめ。
独学のデメリット
1. モチベーション維持が難しい
このモチベーションの維持はめちゃくちゃ大問題。
独学は自由である分、強制力が一切ない。日々の仕事やプライベートの忙しさに流され、気づけば学習計画が大幅に遅れてしまう。なんなら、学習計画すら特に立てずになんとなく学習をしてしまうこともあるだろう。そんなリスクを強要できるか、自分でモチベーションをコントロールし勉強し続けられるか、これがカギ。
2. 学習の方向性に迷いやすい
市販のテキストやネット情報は膨大で、どれを選び、どう進めるかに悩むことも少なくない。定番テキストはもちろんネットで調べればわかる。ただ、そのテキストの中でも重要な内容とそうでない内容がある。その取捨選択を独学で行うのはハードルが高いのは間違いない。なぜなら、そもそも中小企業診断士試験をこれから勉強する人がどこを勉強すればいいのかの取捨選択をうまくできる可能性は低いからである。
効率の悪い学習を続けてしまったり、試験の傾向とズレた対策に時間を割いてしまう危険も多いにある。
3. 最新の試験情報やノウハウが手に入りにくい
予備校や通信講座は、最新の出題傾向や重要論点を的確に教えてくれるが、独学の場合は、それらを自力で収集・分析する必要があり、情報収集力や判断力に差が出やすい現実がある。
短期間で効率よく勉強したい、1発で合格したい、そんな場合は独学よりも予備校や通信講座を利用した方がいい可能性が高いと言えるだろう。
独学が無理な人の特徴と対策
独学が向かない人の共通点
これは間違いなく、「モチベーションの維持ができずに、継続的な学習ができない人」である。
しかし、そもそも常にモチベーションを維持し続けて、継続的な学習が1年以上できる方は、「独学で中小企業診断士に合格できるか」なんて考える前に勉強を始めて勉強をしているはず。
ということは、この共通点を持っている場合がほとんどということである。
ただし、だからといって「独学が不可能」と言っているわけでない。むしろ独学に挑戦してみるもありだと思う。なぜなら、中小企業診断士に合格しても勉強は続く。吸収しなければいけない情報は試験範囲よりも膨大になる。ということはどのみち独学をする力は身につけておかなければいけない。
とあるとだ。中小企業診断士に合格するということと、独学の力を身につけることを一緒にやってしまうのは選択肢としてはありだと思う。
予備校・通信講座の活用を検討すべき人
独学はありだと前述したけれど、「おすすめ」ではない。というのも、中小企業診断士に合格しなければその先はそもそもないからである。
だからこそ、まずは中小企業診断士に合格することをセンターピンにおくことが何よりも重要。となると、何年も勉強し続けることはもったいない。可能な限り短時間で効率よく勉強してさっさと合格して中小企業診断士の実務の中でさらに勉強を進められるようにするのが先決だ。
だからこそ、予備校・通信講座を活用することを本当におすすめする。お金はかかる。決して安くはない金額であることも間違いない。ただ、ここはお金をかけるところだと思う。中小企業診断士になれば絶対にペイできる。
独学でも合格できる!最短ロードマップ
ここまでの内容で、「中小企業診断士試験は独学では難しいのか、、、」と思われている方もいらっしゃると思うが、適切な計画を立てて、適切に勉強を積み重ねていけば独学合格は夢ではなく、現実的に狙えるものである。
しかし、勘違いしてはいけないのは、そもそも独学だろうが、予備校に通おうが中小企業診断士試験は非常に難易度の高い試験であるということ。
一般的に一次試験に必要な勉強時間は800時間から1000時間。二次試験に必要な勉強時間は200時間から300時間と言われている。トータルで考えても1000時間は勉強に費やす覚悟が必要だ。
これが独学であれば、もっと時間が必要になる可能性もある。これが前提。時間・費用・自分のモチベーションを加味して独学で合格を目指すかどうかを決める必要がある。
では、ここからは切り替えて、独学でも合格を目指せるロードマップを一次試験・二次試験に分けて説明をする。
1次試験の学習ステップ
一次試験の学習に関して、さまざまな勉強法や重要論点が至る所で解説されている。もちろん、そのどれも間違いではないはずだ。しかし、ここではシンプルな攻略法をお伝えしたいと思う。
センターピントすべきたった一つのこと。それは、「7科目全ての過去問5年分を1問も間違えずに、不正解の選択肢もなぜ不正解なのか説明できるレベルで頭に叩き込む」ということである。
要は5年分の過去問を完璧にしよう。という戦略である。
どうだろうか?シンプルでわかりやすいと思う。
筆者の経験を踏まえると、一次試験の勉強は下記の3つさえあれば十分合格できる。これらを駆使して、7科目全てでいつでもどこでも100点が取れるようになるまで理解を深めると、ほぼ間違いなく合格できるだろう。
TACスピードテキスト
TACスピード問題集
TAC過去問題集
逆に、これで合格できなければ勉強方法が間違っている。答えを覚えてしまっていたりなど。
とにかくこの3つのテキスト・問題集・過去問をやりきる。これが重要。
具体的な勉強スケジュールに関しては下記のブログで解説しているので是非参考にしてみてほしい。
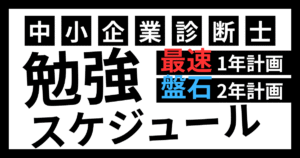
2次試験の学習ステップ
二次試験合格のための基礎知識は一次試験をきちんと勉強していれば申し分ない。あとはその知識を二次試験で”使える状態”にする必要がある。
テキストは下記3つがあれば十分。
中小企業診断士 2次試験合格者の頭の中にあった全ノウハウ
中小企業診断士 2次試験合格者の頭の中にあった全知識
中小企業診断士2次試験 ふぞろいな合格答案
財務会計のみ、苦手な人は専門のテキストを追加で使うことをおすすめする。
30日完成!事例IV合格点突破 計算問題集
ここからは気合いの話にもなるのだが、これらを頭に叩き込む。
あとは、ひたすらに過去問を解きまくる。これでOK。
まとめ|中小企業診断士の独学は本当に無理なのか?
「中小企業診断士 独学 無理」というキーワードで検索しているあなたは、独学での合格が現実的であるのか、不安や迷いを抱えていることが多いはず。
結論として、中小企業診断士試験は独学での合格が不可能というわけでは決してない。実際、独学で合格を果たした受験生も一定数存在しているし、独学により中小企業診断士に合格した後、独学の習慣が強みとなって圧倒的な知識の吸収力を発揮し、大活躍している人もいる。
独学は可能だが戦略が必須
しかし、独学で最も重要だと言えるのは、
「中小企業診断士試験の勉強スケジュールを自ら計画し、モチベーションの有無に関わらずその計画に沿って一つひとつ積み重ねられるかどうか」
である。要は、適切な勉強を適切な量こなす。ということである。
これを確実に実践できなければ、独学は困難であると言わざるを得ない。お金の問題もあると思うが、独学よりも予備校や通信講座を活用した方が貴重な時間を無駄にせずに合格まで迷いなく突き進めるはずだ。
独学か講座かという二者択一ではなく、自身の性格や生活スタイル、合格までの時間的余裕を冷静に分析し、最適な学習手段を選択することが合格への近道であることは間違いない。
中小企業診断士試験は決して簡単な試験ではない。お金もかかる。
ただ、「中小企業診断士 独学 無理」というキーワードで検索しているあなたはもう、スタートラインに立っているようにも思う。
独学だろうが、予備校だろうが、通信講座だろうが、とにかく勉強して知識を身につけていけば必ず合格する。これは絶対だ。
さぁ今すぐ本屋さんに行くか、アマゾンを開くか、予備校のサイトを開くかどれかをしよう。

コメント