「中小企業診断士はうざい」と検索する人は少なくない。上から目線で専門用語を並べる診断士に出会えば、そう感じても不思議ではない。しかし実態は多様であり、頼れるパートナーとして伴走してくれる診断士も存在する。診断士は国家資格であるが独占業務を持たず、その柔軟性ゆえに評価は分かれる。
結論として「一部の診断士は確かに性格や態度が合わない可能性があるが、正しく選べば大きな力になる」。これが答えだと思う。
中小企業診断士とは?役割と実態
中小企業診断士は「経営の総合ドクター」と呼ばれる国家資格である。経営改善から補助金申請、金融機関との調整まで幅広く支援できるのが特徴である。ただし、弁護士や税理士のように独占業務を持たないため、役割は多様であり評価も分かれやすい。診断士の数は全国で約3万人、そのうち独立専業で活動しているのは2割程度にすぎない。この数字は「診断士は増えているが、実力やスタンスに大きな差がある」という現実を示している。
私自身も過去に診断士と補助金の審査会で関わった経験がある。ある人は専門用語ばかりで理解が追いつかず、正直「うざい」と感じた。しかし別の診断士は現場の数字を丁寧に分析し、「ここが改善点だ」と的確に助言してくれた。その瞬間は、まるで霧の中に灯りが差すように課題が明確になった。つまり診断士は「うざい人」もいれば「頼れる伴走者」もいる資格なのである。結局のところ、その印象は資格制度そのものではなく、個々の診断士の姿勢に大きく左右される。
独占業務がない専門家
中小企業診断士には独占業務がない。これは「強み」と「弱み」の両面を持つ宿命である。税理士は税務申告、弁護士は訴訟代理といった専門領域を独占するが、診断士はそうした看板を掲げられない。そのため、営業トークを過度に強める人や、自分を必要以上にアピールする人が出てくる。依頼者から「診断士はうざい」と言われる背景のひとつはここにある。
しかし独占業務がないからこそ、柔軟に企業のニーズに応えられる。例えば「補助金を申請したい」という相談にも、「新規事業の方向性を一緒に考えたい」という要望にも対応できる。いわば“経営の便利屋”ではなく“経営の通訳”のような存在である。難解な財務データを経営者の言葉に翻訳したり、曖昧なビジョンを数値計画に落とし込んだりする姿は、まさに橋渡し役である。
私が出会ったある診断士は、事業計画書を一緒に作る際に「社長、この部分はお客様が笑顔で買ってくれる姿を思い浮かべて書きましょう」と語った。その一言で会議室の空気が柔らかくなり、数字の議論が一気に生き生きとしたものに変わった。独占業務がないからこそ、こうした柔軟で人間的なサポートができるのである。
活躍の場(補助金、経営改善、金融支援)
中小企業診断士の活躍の場は広い。最も身近なのは補助金申請支援である。中小企業庁のデータによれば、事業再構築補助金やものづくり補助金の採択率は診断士が関与した場合に大きく上がるという調査もある。書類作成のコツを知り尽くしているからこそ、採択に向けた「合格答案」を作れるのである。
次に経営改善。売上減少や資金繰り悪化に直面する企業に対して、財務分析やマーケティング戦略を提示する。ここでは机上の理論だけでなく、現場の実態を踏まえた提案が重要である。例えば、地方の製造業では「在庫が山積みになっている倉庫の匂い」をともに嗅ぎ取り、そこから課題を導き出す診断士もいる。五感で感じた課題を言葉にする姿勢が、経営者の信頼を得るのだ。
さらに金融支援の場面でも診断士は力を発揮する。金融機関に提出する計画書をブラッシュアップし、融資担当者に伝わりやすい形で整えることで、資金調達の可能性を高める。私が見たケースでは、診断士が作成した計画書をきっかけに融資が実現し、事業を立て直した中小企業があった。診断士は「うざい存在」ではなく、むしろ経営者にとって背中を押してくれる存在になり得るのである。
「うざい」と言われる理由と実例
「中小企業診断士はうざい」と検索する人がいる背景には、いくつか共通する経験がある。相談の場で上から目線で語られたり、専門用語を並べられて理解できなかったり、営業トークばかりで信用できなかったりするのだ。さらに、現場感覚に乏しく机上の理論を押し付けられると、依頼者は「この人、本当に役に立つのか」と不安になる。
実際に私が目にしたケースでは、補助金の申請相談の席で診断士が「中期経営計画に基づいた財務戦略を再設計すべきだ」と熱弁したものの、経営者は首をかしげるばかりであった。専門用語は飛び交うが、現場の課題である「従業員の離職が多い」という問題には一切触れなかったのである。まるで空腹のときに、栄養素の化学式を説明されるようなものだ。
こうした経験が積み重なると「診断士はうざい」というイメージが定着してしまう。だが全員がそうではなく、裏返せば「伝え方」「スタンス」「現場理解」が整えば信頼される存在になれる。ここからは、具体的にどのような場面で「うざい」と思われがちなのかを掘り下げていく。
上から目線で話す/専門用語が多い
診断士が「うざい」と感じられる典型的な理由の一つが、上から目線の態度である。経営者に対して「御社の財務は脆弱ですね」などと断言すると、助言よりもダメ出しに聞こえてしまう。診断士としては専門的な分析をしているつもりでも、相手には「見下されている」と感じさせやすいのだ。
さらに、専門用語の多用も問題である。「DCF法」「NPV」「ROE」といった言葉を矢継ぎ早に並べられても、経営者にとっては呪文にしか聞こえないことが多い。私が見た現場では、経営者が「結局、私たちの会社は黒字になるのか赤字なのか?」と尋ねると、診断士が「それはキャッシュフローの最適化の問題です」と答えていた。まるで医者に「血圧が高いですか?」と聞いたら「血管内圧の上昇傾向ですね」と返されたようなものである。
診断士の専門性は重要だが、同時に翻訳者の役割も果たさなければならない。つまり、難しい言葉をシンプルに言い換える力が欠けると、一気に「うざい人」という評価に変わってしまうのである。
営業目的が透けて見える
診断士に相談すると、なぜか別のセミナーやサービスを勧められる──そんな経験を持つ人も少なくない。相談者が最も嫌うのは「自分の悩みより、診断士の営業トークが優先される」瞬間である。特に補助金相談をきっかけに「顧問契約を結びませんか」と畳みかけられると、まるでカフェでコーヒーを頼んだら突然「マシンごと買いませんか」と勧められるような違和感を覚える。
もちろん、診断士もビジネスとして活動している以上、営業が必要なのは事実である。ただし、問題はタイミングである。悩みを解決する前に契約を急かせば「結局この人は営業目的だったのか」と失望を招く。逆に、課題解決を丁寧に進めたうえで「継続的にサポートできますよ」と提案すれば、依頼者は安心して契約を検討できる。
つまり、営業の存在そのものが「うざい」のではなく、相手の立場に立たない進め方が「うざさ」を生み出すのである。
経営現場を知らないケース
「机上の空論」という言葉ほど、経営者の心を冷やすものはない。診断士の中には、大企業の理論やMBAの教科書に書かれた内容をそのまま中小企業に当てはめようとする人がいる。しかし、現場には「在庫が積み上がり倉庫の通路が狭くなる匂い」や「パートさんが疲れ切った表情でレジに立つ光景」といった生々しい現実がある。そこを無視して理屈だけを押し付ければ「この人は現場を知らない」と映り、結果として「うざい」と思われてしまう。
私が同行した食品工場の改善プロジェクトでも、診断士が「生産効率を10%上げるべきだ」と言い切った瞬間、現場リーダーは苦笑していた。実際の課題は古い機械の故障であり、人員の努力では解決できない状況だったからだ。現場を見ずに数字だけで語ると、信頼は一気に失われる。
診断士に求められるのは、理論を押し付けることではなく「現場と理論の橋渡し」である。泥のついた作業靴で工場に入り、そこで得た気づきを言葉にできる診断士こそ「頼れる存在」となるのだ。
診断士と上手に付き合うためのポイント
「中小企業診断士はうざい」と感じるか、「頼もしいパートナー」と思えるかは、結局のところ付き合い方次第である。資格そのものは同じでも、診断士の姿勢や依頼者側の準備によって結果は大きく変わる。では、どのようにすれば上手に診断士と付き合えるのか。選び方、依頼前の確認、質問の仕方という三つの視点から整理すると、実務にすぐ役立つ。
例えば、私がかつて支援に同席した食品メーカーでは、最初に診断士の経歴を細かく聞いたうえで、あえて工場見学をお願いした。結果、診断士は機械油のにおいや作業現場の空気感を体感し、机上の提案ではなく現場を踏まえた改善策を提示してくれた。このように依頼者側が関わり方を工夫するだけで、「うざい」診断士が「ありがたい存在」に変わることも少なくない。
診断士と向き合う際には、「この人なら信頼できる」と確信できる材料を集めることが肝要である。そのためには基準を持ち、確認事項を整理し、具体的な質問をぶつけることが効果的なのである。
選び方の基準(経験・実績・相性)
診断士を選ぶとき、最初に見るべきは「経験と実績」である。補助金の採択支援件数や過去に関わった業界など、具体的な数字や事例を確認することで力量を測れる。数字は嘘をつかないが、同時に「相性」も無視できない要素である。たとえば、経営者の話を遮らず最後まで耳を傾けてくれる診断士は、それだけで信頼感を生む。逆に数字の実績が立派でも、会話がかみ合わない相手とは長期的な関係は築きにくい。
私が見たケースでは、ある診断士が「社長、それは無理です」と冷たく突っぱねる一方で、別の診断士は「確かに難しいですが、こう工夫すれば可能性があります」と前向きに提案していた。両者の実力は同等でも、依頼者の満足度は雲泥の差であった。診断士の力量は「数字+相性」で測るべきだというのが私の解釈である。
依頼前に確認すべきこと
診断士に相談する前に、依頼者自身が準備しておくべきことがある。まず「何を期待するのか」を明確にすることだ。売上改善なのか、補助金申請なのか、資金繰り支援なのか。目的があいまいだと、診断士の提案も散漫になりがちである。また、料金体系や契約形態も事前に確認しておくことが重要である。後から「こんなに費用がかかるとは思わなかった」と感じれば、せっかくの支援も不信感に変わってしまう。
ある経営者は、初回面談の際に「成果報酬型ですか?固定費ですか?」と必ず確認するそうだ。これだけでも余計なトラブルを避けられる。診断士との付き合いは結婚に似ている。最初に条件を確認しないまま勢いで進めれば、後で後悔する可能性が高い。冷静な準備こそが「うざい」と感じない関係を築く第一歩である。
失敗しないための質問リスト
診断士と話すときに、漠然と「お願いします」と丸投げしてしまうと後悔しやすい。そこで役立つのが「質問リスト」である。例えば以下のような質問は効果的である。
- 過去に支援した案件で最も印象的だった成功例と失敗例は?
- 自分の業界での支援経験はあるか?
- 具体的な支援の進め方はどのような流れか?
- 万が一、成果が出なかった場合はどうフォローするか?
こうした質問を通じて、診断士の経験値やスタンスが浮き彫りになる。私が立ち会った場面では、ある診断士が「失敗例も隠さず話します。そこから学んだことが今の支援に活きています」と答え、経営者は一気に安心した様子であった。質問は相手を試すものではなく、信頼を築く入口である。準備した質問リストが、診断士を「うざい存在」から「心強い伴走者」へと変える鍵になるのだ。
まとめと判断基準
ここまで見てきたように「中小企業診断士はうざい」と言われるのには理由がある。しかし、それは資格制度自体の欠陥ではなく、個々の診断士の姿勢や依頼者側の受け止め方に左右される部分が大きい。つまり「頼れる診断士」に出会えるかどうかは、選び方と関わり方次第である。
診断士は全国で約3万人いると言われ、その中には机上の理論ばかりを振りかざす人もいれば、現場に入り汗をかきながら伴走してくれる人もいる。依頼者にとって大切なのは「うざい診断士」と「頼れる診断士」の違いを見極め、自分の会社にとって最適な相手を選ぶことである。そのためには依頼前に正しい判断基準を持つことが不可欠である。ここでは最後に、その具体的な視点を整理する。
「うざい診断士」と「頼れる診断士」の違い
「うざい診断士」と「頼れる診断士」の違いは、表面的な態度以上に「依頼者目線で考えているかどうか」にある。うざい診断士は専門用語を並べて自分の知識を誇示しがちである。逆に頼れる診断士は、難しい理論をかみ砕き、経営者が現場で使える言葉に置き換える。これは医者が患者に「高血圧症」とだけ言うか、「塩分を減らせば改善できます」と具体的に助言するかの違いに似ている。
私が取材した企業では、ある診断士が「売上高営業利益率が低いですね」と切り捨てた一方で、別の診断士は「商品の回転が遅いので、仕入れを週3回に増やしましょう」と現場レベルで提案していた。結果、後者の提案は数字改善につながり、経営者の信頼を大きく勝ち取った。数字を語ること自体は重要だが、それを実行可能な形に変換できるかどうかが分かれ目なのである。
つまり「うざい診断士」は自己中心的な伝え方をする人、「頼れる診断士」は経営者の立場に立ち、実行可能な道筋を示す人である。この違いを意識するだけでも、依頼先選びの精度は格段に高まる。
依頼前に持つべき視点
診断士を依頼する前に大切なのは「診断士に何を求めるのか」を明確にする視点である。補助金申請を通したいのか、売上改善に取り組みたいのか、資金繰りを安定させたいのか。目的があいまいなまま依頼すると、診断士の提案もピントがずれがちになる。
さらに「現場を理解してくれるか」を確認する視点も欠かせない。例えば工場の現場で油のにおいや機械の振動を一緒に感じながら改善点を語れる診断士は、机上だけのアドバイザーより信頼感が圧倒的に増す。数字や理論を現場のリアルと結び付けて話せるかどうかが、信頼できる診断士の判断基準になる。
最後に「相性を見極める視点」も重要である。数字の分析が得意でも、コミュニケーションが合わなければ長期的な支援は難しい。初回面談で違和感を覚えたら、その直感は軽視しない方がよい。診断士との関係は短期の取引ではなく、時に数年単位で続く「経営の伴走」である。だからこそ、冷静に複数の診断士を比較し、自社に合う相手を選ぶ姿勢が必要なのである。
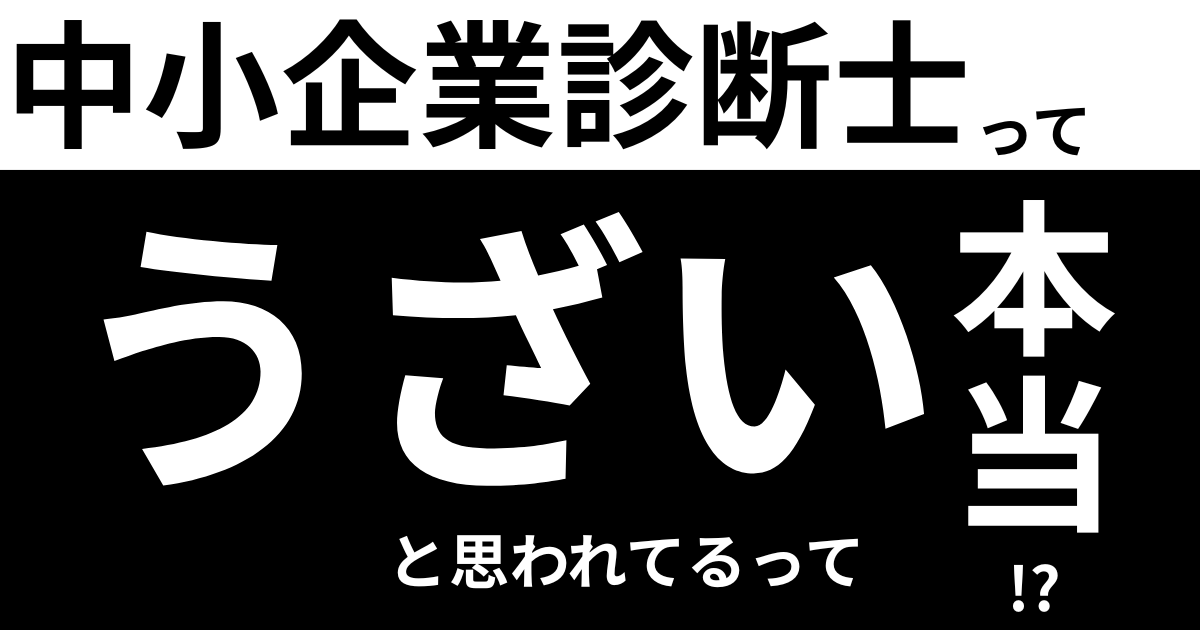
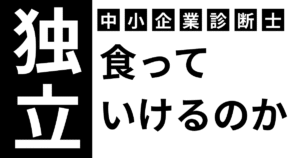

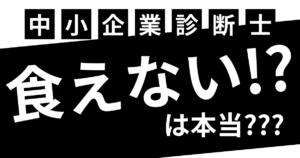
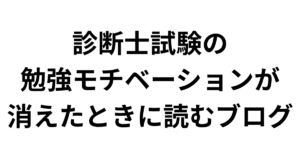
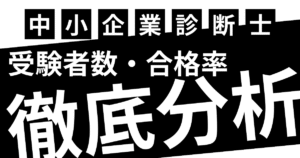
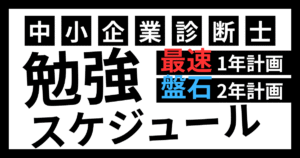

コメント