「中小企業診断士は食えない」。検索窓にこの言葉を入れている時点で中小企業診断士の資格に一抹の不安を感じているのは確かなはず。
だが、実際の現場データ、例えば、協会アンケートや中小企業白書を丁寧に読むと、そこにあるのは独立して食えるか食えないかは“無理ゲー”ではなく“設計の問題”であるということだ。独占業務がない以上、営業は必須であり、収入はレンジで分布する。公的支援に寄りかかりすぎれば単価は伸びにくいが、専門特化と継続導線を設計すれば「中小企業診断士=食えない」という固定観念は崩れる。
中小企業診断士として“食える現実”は、派手な裏ワザではなく、小さな専門と継続の仕組みの積み上げで到達可能である。
なぜ「診断士は食えない」が語られるのか(事実と誤解)
「中小企業診断士は食えない」という言葉は、ネット検索をすれば必ず目に入るフレーズである。資格学校のパンフレットを開けば希望に満ちたキャッチコピーが並ぶ一方で、SNSでは「結局副業止まり」「独立しても仕事がない」というニュアンスの言葉を見かけることもある。
このギャップはどこから生まれるのか。
実態を冷静に整理すると、構造的な制約と誤解が入り混じっていることが見えてくる。
まず事実として、診断士は弁護士や税理士のような「独占業務」がない。つまり、資格を持っていなくても似たような支援をできる人は多く存在する。加えて、顧客を獲得するためには自ら営業活動を行う必要があり、資格を取った瞬間に案件が降ってくるわけではない。これを知らずに飛び込むと、肩書きだけで食べていけると勘違いしやすい。
一方で、誤解も多い。たとえば「収入はほとんどゼロ」という言説があるが、現実には独立初期でも月20〜40万円程度のレンジで収益を上げる人は一定数存在する。もちろん、この金額だけで生活を安定させるのは難しいが、会社員時代の貯蓄や副業との組み合わせで乗り切る診断士も少なくない。冷蔵庫の残り物でなんとか週末の晩ごはんを工夫するのと同じで、「足りない前提での設計」がカギとなる。
さらに、公的支援に依存しすぎるリスクも見逃せない。補助金申請や自治体案件は参入障壁が低いため競合が多く、単価が安定しづらい。ここで「食えない」という声が生まれやすい。しかし逆に考えれば、ここを起点に民間企業支援や自らの専門分野に展開できれば、差別化と安定収益化につながる。要するに「食えない」の本質は資格そのものの限界ではなく、導線設計の欠如にあるのである。
独占業務なし×営業必須の構造
診断士が「食えない」と言われる最大の理由は、独占業務がないことであると言えるのではないだろうか。
税務申告なら税理士、登記なら司法書士といったように、法律で守られた領域がないため「資格を持っているから自動的に顧客が来る」という構造がない。診断士の仕事は、いわばオープンカフェの席取りのようなもので、資格を持たない経営コンサルタントや金融機関出身者とも同じ土俵で競争する。
そのため、案件獲得には営業力が不可欠となる。人によっては、資格勉強よりも「営業活動のほうが難しい」と口にするほどである。
実際、資格を取ったからといって自動的に顧客が用意されるなんてことはなく、自分のポジションを示す自己PRが必須で選ばれる診断にならなければいけない。しかも選ばれるためには、営業活動が必須である。
とはいえ、営業必須というのは裏を返せば「努力次第で差別化できる」余地があるということだ。診断士全体で見ると、営業やマーケティングに苦手意識を持つ人が多い。その中で「自分から動ける診断士」はむしろ目立ちやすく、実績を積むチャンスがある。要するに「営業必須=参入障壁」ではなく、「営業必須=差別化チャンス」と読み替えることが生存戦略である。
独立初期1〜2年の収入レンジと必要な資金クッション
独立直後の診断士の収入は、一人暮らしアパートの家賃ぐらいにしかならない時期があるのも事実である。実際に独立1年目のアンケートでは、年収100万円未満が約4割を占めるとされている。一方で、順調に案件を得られた人は年収300〜500万円程度に達することもある。つまり、レンジが非常に広いのが特徴である。
ここで重要になるのが「資金クッション」である。
会社員を辞めてすぐに独立した場合、生活費と事業投資が同時に重くのしかかる。たとえば、PCの買い替えや交通費、交流会の会費など、毎月の固定費は軽く10万円を超える。これを支える貯蓄がなければ、案件が決まる前に息切れしてしまう。実際、私の知人は半年分の生活費を貯めずに独立したが、安定的な収入を得るまでには時間がかかっていた。
一方で、十分な資金クッションを持っている人は、腰を据えて営業活動や専門領域の構築に時間を割ける。その差は1年後には歴然となる。診断士の独立は短距離走ではなくマラソンである。スタート直後に全力疾走してバテるのではなく、走り切るための「体力=資金クッション」を準備しておくことが不可欠である。
公的支援依存のリスクと代替戦略
診断士が独立直後に頼りやすいのが、公的支援案件である。補助金申請や経営相談窓口など、比較的参入しやすく安定した需要がある。しかし、この分野は競合が多く、報酬単価も限られている。まるでコンビニの100円コーヒーのように「とりあえず需要はあるが、単価は上がらない」構造である。
この依存構造には2つのリスクがある。第一に、制度変更や予算縮小によって突然案件が減る可能性がある。第二に、経験が公的案件に偏ると、民間企業から「補助金屋」と見られ、コンサルティングの幅が狭まる。診断士のキャリアが「安定」から一転して「不安定」へと揺らぐのは、この構造が背景にある。
では代替戦略は何か。ひとつは「専門分野を持つ」ことである。たとえばマーケティング、DX、人材育成など、自分の強みを打ち出すと民間企業への展開が容易になる。もうひとつは「営業チャネルの分散」である。紹介や協会経由に加えて、Web集客やSNS発信を組み合わせることで、案件依存度を下げられる。実際に、SNSからの問い合わせで年間売上の半分を獲得した診断士も存在する。
公的案件は入口として活用しつつ、早い段階で「自分ならではの領域」に転換することが、食えない診断士と食える診断士を分ける分岐点である。
一次データで見る“到達可能な現実
「診断士は食えない」と繰り返し言われる一方で、現場の一次データを冷静に見れば、むしろ「到達可能な現実」が浮かび上がってくる。資格取得直後にいきなり年収1,000万円というのは宝くじのような話である。しかし、協会アンケートや中小企業白書に示された数値を読み解くと、独立後の活動実態や伸び筋領域は決して幻想ではない。むしろ、再現性を持って追える軌跡がある。
データは無味乾燥に見えるが、その背後には生活のリアルが宿る。朝の通勤電車でスーツに汗をにじませながら副業の原稿を仕上げる診断士。補助金申請支援で夜中まで事務所の蛍光灯に照らされる診断士。こうした姿は統計のグラフには出てこないが、アンケートの数字と結びつければ現実感を伴う。
一次データが示すのは、「診断士としての活動は安定性に欠けるが、多様な可能性が広がっている」ということだ。協会の調査からは収入や活動時間の幅が、白書の事例からは成長領域の存在が明らかになる。つまり、到達可能な現実とは「安易な成功神話」ではなく、「地に足のついたステップアップの積み重ね」である。資格を取ることは入口に過ぎず、データはその先の道標を示しているのである。
協会アンケートで把握する活動実態
中小企業診断協会が実施するアンケート調査は、診断士の実態を把握する上で重要なデータソースである。たとえば、直近の調査では「年間収入が300万円未満」の層が独立診断士の中で約4割を占める一方、「700万円以上」の層も約2割存在している。つまり、ゼロか100かの話ではなく、収入レンジは広く分布しているのが実態である。
また、活動内容の内訳を見ると、公的機関案件への依存度が高い人と、企業のコンサルティングを主軸にする人とで構造が二分している。アンケートの数字は一見バラバラだが、「診断士のキャリアパスは多様である」という現実を示している。ある人は月数件の補助金支援でコツコツ稼ぎ、ある人は研修講師として全国を飛び回る。駅弁の種類が多すぎてどれを選ぶか迷う旅人のように、診断士も進む道を選び取る必要がある。
協会アンケートは単なる統計ではなく、「このレンジに収まる現実が待っている」と教えてくれる羅針盤なのである。
筆者が交流会で出会った独立2年目の診断士は、初年度は年収200万円程度だったが、営業を強化した2年目には研修案件を複数獲得し、500万円台に到達したという。数字の裏には「努力と方向転換による成果」が確かに存在する。
ちょっとSNSに目を向けると簡単に1000万円を超えられる!という発信を見かけることがある。ただし、その裏には努力や実行力があることを忘れてはいけない。
最初から高望みをすることなく、一歩一歩愚直にお客様の求める成果の創出に向き合っていった先に結果がついてくるのだと思う。
中小企業白書の事例から見る伸び筋領域
もうひとつの貴重な一次データが「中小企業白書」である。ここには全国の企業事例が多数収録されており、診断士がどの分野で活躍できるのかを示すヒントが隠されている。近年特に目立つのは、デジタル化・事業承継・海外展開といったテーマである。
たとえば、白書に掲載された地方製造業の事例では、DX導入を支援した外部専門家が売上回復の起点になったと紹介されている。この「外部専門家」の一部に診断士が含まれており、IT導入補助金や生産性向上のアドバイザーとして実績を積んでいる。紙の伝票からクラウド会計へ切り替わる瞬間の現場の空気感──戸惑いと安心が入り混じった社員の表情──は、診断士が介在する余地の大きさを物語っている。
さらに、後継者不在の中小企業において、事業承継支援を行う診断士のニーズも高まっている。白書が示す事例の多くは、金融機関や士業と連携して進められており、診断士は「ハブ役」として位置付けられる。この分野は単価も高く、持続的に案件が発生する可能性が高い。
つまり、中小企業白書を参照すれば、「どの領域で伸び筋があるか」という現実的な解が見えてくる。公的案件に偏りすぎるリスクを回避しつつ、デジタル化や事業承継などの成長領域に参入することが、診断士にとっての“食える現実”を作り出す戦略である。
まとめ
結局、「中小企業診断士は食えない」の主語は大きすぎる。食えるかどうかは、①誰のどの課題を解くか(専門の定義)、②どう続けるか(継続導線の設計)、③いくらで、何をもって成果とするか(価格とKPI)の三点で決まる。一次データはそれを裏付ける。収入はレンジで分布し、公的依存は天井を作りやすいが、民間比重と顧問化は継続性を高める。白書の事例は、DXや事業承継など“伸び筋”が確かにあることも示している。
中小企業診断士は食えないのではない。設計がなければ食えないのである。設計を持てば、食えるのである。今日決め、今書き、次の打合せで提案する。検索の不安を行動の設計図に変えた瞬間から、物語は静かに逆転していく。
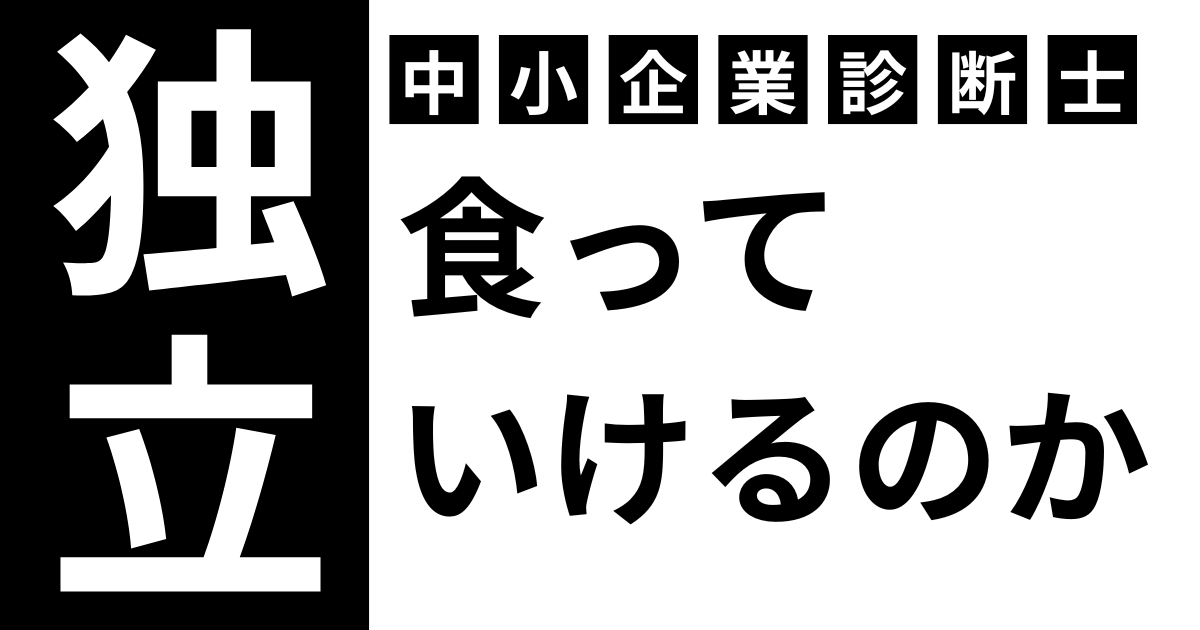

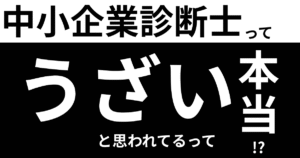
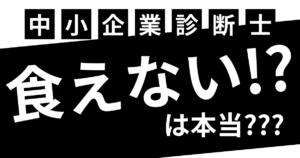
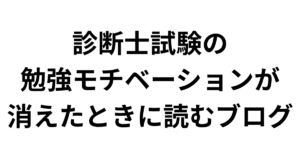
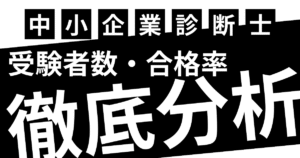
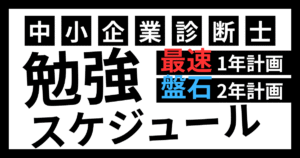

コメント