中小企業診断士の現状 — 食えないと言われる背景とデータ
「中小企業診断士は食えない」と耳にしたことがある人は多いだろう。まるで「資格を取っても冷蔵庫の中がスカスカになる」かのようなイメージである。しかし実際には、その背景には数字や構造的な事情が存在している。登録者数の増加、公的支援案件の偏重、そして資格の社会的評価のギャップ。この3つが複雑に絡み合い、診断士の現状を形づくっている。
たとえば私自身、診断士と名刺交換をする機会があるが、その働き方は実に多様である。大企業に勤めながら副業的に活動する人、補助金支援をメインに事務所を構える人、あるいは完全に独立して中小企業経営者と伴走する人。数字で見れば「食える診断士」も確かに存在するが、全体を平均化すると「食えない」と言われても仕方がない分布になっているのが現実である。
ここで重要なのは「資格を取れば安定収入」という発想を捨てることだ。医師や弁護士と違い、診断士には独占業務がない。そのため営業力や人脈形成が必要不可欠である。つまり、資格はゴールではなく「スタートライン」に過ぎないのである。冷蔵庫を満たすのは資格そのものではなく、資格をどう活かすかの行動次第だということだ。
登録者数・独立診断士の割合の推移(一次情報/協会データ)
中小企業診断士協会のデータを見ると、登録者数は年々増加している。2020年時点で約3万人だった登録者は、直近では3万5千人を超えている。数だけ見れば「右肩上がり」である。しかし注目すべきは、その中で独立診断士の割合が2割程度にとどまっている点である。つまり、ほとんどの診断士が副業や企業内での資格活用にとどまっている。
この構造は、まるでスポーツジムの会員数に似ている。会員は年々増えているが、実際に通って汗を流す人は限られている、という状況である。資格を取る人は増えているのに、独立に踏み切れる人は少ない。これは収益モデルが安定していないことを示している。
一方で、独立している診断士の中には「100日以上稼働し、年収1,000万円以上」という層も存在する。要するに「少数精鋭」で食えている人と、多数派として資格を持ちながらも活かしきれていない人の二極化が進んでいるのが現状である。
公的支援案件・補助金支援などの需要動向
診断士の主要な仕事のひとつは、公的支援案件や補助金申請の支援である。特に「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」といった制度は、企業からのニーズが高い。事実、中小企業庁の調査によれば、診断士が関与する案件の過半数が公的支援に関連している。
ただし、このモデルにはリスクもある。補助金は制度変更や予算の増減に左右されるため、案件数が安定しない。診断士仲間からは「年度末は忙しくて寝不足、年度初めは暇で焦る」といった声も聞かれる。まるで夏祭りの屋台商売のように、シーズンごとに波があるのである。
一方で、民間企業からの直接コンサルティング案件はまだ十分に拡大していない。補助金依存度が高い構造のままでは、「食えない診断士」という評価は消えにくい。持続的に案件を確保するには、公的支援の枠を超え、経営戦略や人材育成といったテーマで企業と深く関わる必要がある。
認知度・資格の価値・社会的評価のギャップ
「診断士って何の資格?」と問われた経験がある人も多いだろう。これはまさに認知度の低さを象徴するエピソードである。弁護士や税理士といった資格に比べ、中小企業診断士の社会的認知度はまだまだ低い。
実際、中小企業白書のアンケートでも、経営者の多くが「診断士の存在を知らない」「役割を理解していない」と回答している。知名度が低いということは、企業側からの自発的な相談が少なく、診断士側が営業をかける必要があるということだ。
とはいえ、現場での価値は確実に存在する。資金繰りに悩む社長から「診断士に相談してよかった」と感謝される場面もある。つまり「食えるかどうか」は、資格そのものよりも「どう伝え、どう信頼を獲得するか」にかかっている。資格の認知度と現場での体感価値のギャップを埋めることこそ、今後の診断士に求められる課題である。
なぜ“食えない”と言われるのか — 主な原因の整理
中小企業診断士が「食えない資格」と言われる理由は一つではない。資格そのものの構造的な特徴から、活動を続ける上での環境要因まで複数の要素が絡んでいる。よくあるのは「独占業務がないため差別化が難しい」「営業力やネットワークが不足して案件を獲得できない」「収益モデルが不透明で、独立初期は収入が安定しない」という三つの要因である。
これは料理にたとえるとわかりやすい。レシピ本を読んだだけでは美味しい料理は作れない。材料の仕入れ(案件獲得)、調理の技術(専門知識の活用)、盛り付けの工夫(差別化戦略)が揃って初めてお客は喜ぶ。診断士資格はレシピ本のようなものであり、それだけでは食卓に料理は並ばないのである。
現場の声としても「資格を取ってからの方が学びの連続だった」という意見が多い。資格取得直後は名刺に「診断士」と書けるようになった安心感がある一方、実際には仕事の依頼が舞い込むことは少ない。資格は入り口であり、そこで止まってしまえば“食えない”という評価につながるのは必然である。
独占業務がないことと差別化の難しさ
中小企業診断士が直面する最も大きな問題のひとつは「独占業務がない」という点である。弁護士なら裁判、税理士なら税務申告というように、資格を持っていなければできない仕事がある。しかし診断士にはそれが存在しない。つまり、誰でも似たようなサービスを提供できるため、差別化が難しいのである。
実際に経営者と話すと「診断士と経営コンサルタントって何が違うの?」と聞かれることが多い。名刺を差し出した瞬間に説明を求められるのは、ある意味でこの資格の宿命である。独占業務がない分、自分自身の専門分野を明確に打ち出す必要がある。たとえば「補助金申請の支援に特化する」「製造業の改善指導に強みを持つ」といった差別化がなければ、他のコンサルタントと埋もれてしまう。
まるで駅前のカレー屋が乱立しているような状況である。看板に「カレー」とだけ書いても客は入らない。スパイスの香りや限定メニューといった“ここにしかない理由”を示すことが、診断士として生き残るための必須条件である。
営業力・ネットワーク不足・案件獲得のハードル
資格を取っただけで仕事が舞い込むことはない。むしろ本当の勝負は資格取得後に始まる。特に独立を考える診断士にとって、最大の壁は「営業力」と「ネットワーク」である。知識や資格がどれだけあっても、それを必要とする経営者に出会えなければ仕事は始まらない。
実際、ある調査によると独立診断士の約3割が年間売上300万円未満にとどまっている。これは案件獲得がうまくいかない典型例である。知人の診断士も「勉強よりも営業が大変だ」と嘆いていた。セミナーでの登壇や異業種交流会への参加、金融機関や士業との連携など、地道な営業活動が必要不可欠なのである。
営業が得意ではない診断士にとって、この壁は心理的にも大きい。名刺交換で一言添えるだけでも緊張する人は多いだろう。だが、ここを避けて通れば“食えない”という現実に直結する。案件獲得のハードルをどう乗り越えるかが、診断士の収益性を大きく左右するのである。
収益モデルが見えにくい・初期期間の収入が低い問題
診断士として独立しても、すぐに安定収入が得られるわけではない。むしろ最初の1〜2年は、収益モデルが見えず不安を抱える人が多い。公的支援案件に頼れば一定の収入は得られるが、予算や制度に左右されやすく、年間を通じた安定性は低い。
独立直後の診断士の平均年収は300万〜400万円程度とも言われており、生活費を考えると決して余裕のある水準ではない。資格取得にかけた時間や費用を考えると「投資回収が見えない」と感じる人も多いだろう。
私自身も知り合いの診断士から「冷蔵庫の中身を見て焦った」と聞いたことがある。資格は取ったが案件が少なく、スーパーの特売日を狙って買い物をする生活になったという話だ。まさに“食えない”という言葉を実感する瞬間である。
ただし、この時期をどう乗り越えるかで未来は変わる。補助金依存から脱却し、顧問契約やリピート案件を積み上げることで収益モデルは安定していく。最初の低収入を耐え抜けるかどうかが、診断士として食えるか否かの分岐点になるのである。
“食える”診断士とはどんな人か — 成功者の事例分析
「中小企業診断士は食えない」とよく言われるが、実際には“食えている”診断士も確実に存在する。では、どんな人がその成功例に当たるのか。ここでは、三つのパターンに分けて分析する。専門分野を持ち差別化に成功した人、企業内で安定収入を確保している人、そして副業・兼業で資格を活用している人である。
彼らに共通するのは「診断士資格を軸に、自分なりのストーリーを作っている」という点である。資格を持っているだけでは何も始まらない。だが、自分の強みや環境に合わせた活かし方を見つけた診断士は、しっかりと収益を確保している。まるで同じカメラでも、人によって撮れる写真が全く違うように、資格の活かし方次第で結果は大きく変わるのである。
専門分野を持って成功しているケーススタディ(例:地域特化/補助金以外のサービス)
独立して成功している診断士の多くは「専門分野を持っている」ことが特徴である。たとえば地域特化型で「地元製造業の改善支援」を強みにした人、あるいは補助金以外のサービス、例えば「人材育成」「DX推進」「マーケティング戦略」に特化した人である。
ある地方都市で活躍する診断士は「地元商店街の売上改善」に注力している。商店街の会議室で冷たいお茶を飲みながら「お客さんの足音が減っているのをどう止めるか」という議論を重ね、イベント企画や店舗リニューアルにまで関与した。結果、地域全体で売上が前年より15%改善したという。数字以上に、現場の熱気や笑顔が報酬に直結するのは診断士ならではのやりがいである。
専門分野を持つことは、いわば「店の看板」を掲げることに近い。看板がなければお客は立ち寄らない。食える診断士になるには「自分は何屋なのか」を明確にすることが、最初の一歩である。
企業内診断士として安定収入を確保している例
もう一つの成功パターンは「企業内診断士」である。独立せず会社員として働きながら、診断士資格を業務に活かすスタイルである。実際、大手企業や金融機関では「診断士資格を持つ社員」を評価する制度が存在する。昇進や人事評価に直結する場合もあり、安定した給与に加えて資格による付加価値を得られるのが強みである。
たとえば、地方銀行に勤めるある診断士は「融資先の経営改善提案」を日常業務に組み込み、上司から高い評価を得ている。銀行員としての収入を得ながら、診断士としての専門性を発揮できるため、リスクは低くリターンは確実だと言える。
このスタイルは、まるで定食屋の「日替わり定食」のような安心感がある。大きな冒険はないが、安定した収入と経験が積み重なっていく。独立志向が強くない人にとっては、最も堅実な“食える診断士”の形である。
兼業・副業で収入を補っている例
三つ目は「兼業・副業」で収入を補っているケースである。近年、副業解禁の流れもあり、会社員として働きながら週末や夜に診断士として活動する人が増えている。
実際、ある診断士は平日はメーカー勤務、休日は商工会議所の経営相談員として活動している。月に数回の相談業務で追加収入を得つつ、実務経験を積んでいる。生活費の不安は本業でカバーしつつ、副収入とスキルアップの両方を実現しているのだ。
この兼業スタイルの魅力は「リスク分散」である。独立一本に絞れば収入が不安定になりがちだが、副業なら安心感がある。例えるなら、冷蔵庫に常備菜がある安心感に近い。日々のご飯に困らず、時折ごちそうを楽しめる余裕が生まれる。
結果的に副業で経験を積んだ後に独立へシフトする人も多い。つまり、副業は単なる収入補填ではなく「未来へのステップ」になり得るのである。
“食いっぱぐれない”ための戦略と具体的アクションプラン
中小企業診断士として“食えない”状態を避けるには、資格を取った後にどのような戦略を描くかが重要である。資格そのものは切符に過ぎず、どの列車に乗るかは自分次第である。成功している診断士に共通するのは「得意領域を見極める」「情報発信で存在を知ってもらう」「営業チャネルを体系的に構築する」「収益とコストを管理する」というシンプルだが実行力のいる行動である。
多くの診断士が直面する現実は、資格を取っただけでは案件が降ってこないという事実だ。だからこそ、自分の強みを市場と接続する工夫が必要になる。SNSやWebサイトでのブランディング、ネットワークの拡張、そして地味だが重要なコスト管理。こうした戦略的アクションを組み合わせることで、診断士としてのキャリアを“食いっぱぐれない”形に変えていけるのである。
得意領域・ニッチ領域の選定方法
診断士がまず取り組むべきは「得意領域の選定」である。資格の守備範囲は広いため、何でもできますと言ってしまいがちだが、それでは差別化にならない。たとえば「飲食業の原価管理」「地方製造業の改善」「小売のDX推進」といった具体的なニッチ領域を打ち出す方が案件につながりやすい。
実際に知り合いの診断士は「食品スーパーの棚割最適化」を得意領域にした。最初は趣味の延長のようにデータ分析を始めたが、気づけば複数チェーンから顧問契約を得て安定収入につながったという。数字に強い、現場に入りやすい、人と話すのが得意――こうした自身の特性をベースにニッチを決めることが成功の近道である。
市場を観察し、自分のスキルと掛け算できるテーマを探す。これはまるでスーパーの買い物で「今日はカレーを作る」と決めてから材料を選ぶのと同じである。先にテーマを決めることで無駄な買い物が減り、料理がまとまる。診断士としても先にテーマを定めることで活動がスッキリと整理されるのである。
マーケティング/情報発信/ブランディング(Web・SNS含む)
診断士としての存在を知ってもらうには「発信」が欠かせない。今やSNSやブログは名刺以上の自己紹介ツールであり、情報を届けることで信頼を獲得できる。特に「補助金情報」「経営改善の実例」「最新トレンドの解説」といった実務に役立つ情報は経営者に響きやすい。
ある診断士は週に1回ブログを更新し、そこから年間10件以上の案件を獲得している。記事を読んだ経営者から「相談したい」とメールが届く瞬間は、努力が実を結ぶ場面である。Web上の文章は、眠っている間も営業してくれる24時間の看板のような存在である。
ブランディングとは、単にカッコいいデザインを作ることではなく「何を得意とする診断士か」を一貫して発信し続けることにある。SNSのプロフィールや記事タイトルに専門領域を明確に書くことは、SEO的にも効果がある。地道な発信が積み重なれば「この分野といえばあの人」という評価につながり、“食いっぱぐれない”基盤になる。
営業チャネルを作る方法(ネットワーク、公的案件、顧問契約 etc.)
案件を継続的に確保するためには「営業チャネルの複線化」が不可欠である。診断士の多くは最初、公的案件や補助金支援に依存する。しかしこれだけでは安定しない。そこで人脈を広げ、顧問契約や紹介案件といった複数のチャネルを作ることが重要になる。
実際に成功している診断士の多くは「公的案件+民間顧問+セミナー登壇」といった形で三本柱を築いている。特に顧問契約は安定収入につながりやすく、月額数万円でも複数社を積み上げれば年間で大きな柱となる。
また、営業活動を続けると「誰かを紹介される」機会が増える。名刺交換やちょっとした雑談から案件が生まれることも少なくない。これはまるで飲み会で隣に座った人と意気投合し、次の週に一緒にランチをしているような自然な流れである。診断士にとって営業チャネルとは作り込むものでもあり、同時に日常の人間関係から自然に生まれるものでもある。
コスト管理・維持要件・リスク回避のポイント
診断士として活動する際に見落とされがちなのが「コスト管理」である。独立すると名刺代や交通費、Webサイトの維持費、協会費用など固定的に出ていく支出が増える。これらを把握せずに活動を続けると、利益が思った以上に残らないという事態に直面する。
ある診断士は「月に5万円の経費をどう稼ぐか」という目標を立て、それ以上を利益と位置づけた。このシンプルな考え方が事業継続を支える。固定費を抑えるだけでなく、変動費も意識することで精神的な余裕が生まれる。
リスク回避の観点では、収入源を一つに依存しないことが肝心である。補助金案件がゼロになっても顧問契約があれば生活は安定する。逆に顧問先が解約になってもセミナー収入があれば補える。複数のポケットにお金が入る状態を作ることで、不測の事態にも耐えられる。診断士が“食いっぱぐれない”ためには、稼ぐだけでなく守る戦略も必要なのである。
まとめと判断基準
ここまで見てきたように、中小企業診断士が「食えるかどうか」は資格そのものではなく、その後の戦略と行動にかかっている。独占業務がない分、差別化が難しく、営業やネットワーク構築に時間がかかるのは事実である。しかし一方で、専門性を磨き、ブランディングを行い、収益モデルを複線化した診断士は確実に“食える”存在になっている。
結局のところ、判断基準は「資格取得をゴールにするのか、スタートにするのか」である。名刺に肩書を載せるだけで安心するなら“食えない”可能性は高い。しかし、資格を軸に自分の強みを市場に接続しようとすれば、診断士はむしろ武器になる。資格取得後の行動が未来を分けるのである。
あなたが「食える診断士」になるためにまずすべきこと
食える診断士になるために、まずすべきことは「自分の得意領域を明確にすること」である。補助金、財務改善、マーケティング、DX支援など何でも手を出すのではなく、まずは一つの柱を立てることが重要である。
たとえば、ある知人の診断士は「飲食店の原価管理」に特化した。最初は小さな居酒屋の相談から始まり、やがて口コミで広がり、地域の飲食業界の“お抱え診断士”となった。これは偶然ではなく、自分の強みを一点に集中させたからこそ得られた成果である。
さらに行動としては、①専門分野の情報を継続的に発信する、②ネットワークを拡大する、③最初の実績を早く作る、の三つを意識すると良い。特に実績は名刺よりも強力な営業ツールになる。「あの店の売上を伸ばした人」という肩書は、数字とセットで相手の心に響く。資格そのものより、体験と成果を積み重ねることが“食える診断士”の第一歩である。
資格取得後のロードマップ例
資格を取った後に迷わないためには、ロードマップを描いておくことが有効である。以下は一例である。
- 1年目:公的案件や商工会議所の相談員などを通じて経験を積む。副業でも構わないので現場経験を増やす。
- 2〜3年目:得意分野を明確化し、情報発信を継続。SNSやブログを活用して専門性を可視化する。同時に顧問契約やリピート案件を意識的に増やす。
- 4〜5年目:安定収入の柱を2〜3本持つ。たとえば「公的案件+顧問契約+セミナー登壇」といった複線化を実現する。
- 6年目以降:独自ブランドを確立し、「この分野ならこの診断士」と言われるポジションを確立する。
この流れはまるでマラソンのようである。最初から全力疾走するのではなく、序盤は地道に走り、中盤でペースをつかみ、後半で成果を積み上げる。診断士人生も同じで、資格取得はスタートの号砲に過ぎない。計画的にロードマップを描くことで、食いっぱぐれない未来を自ら選び取ることができる。
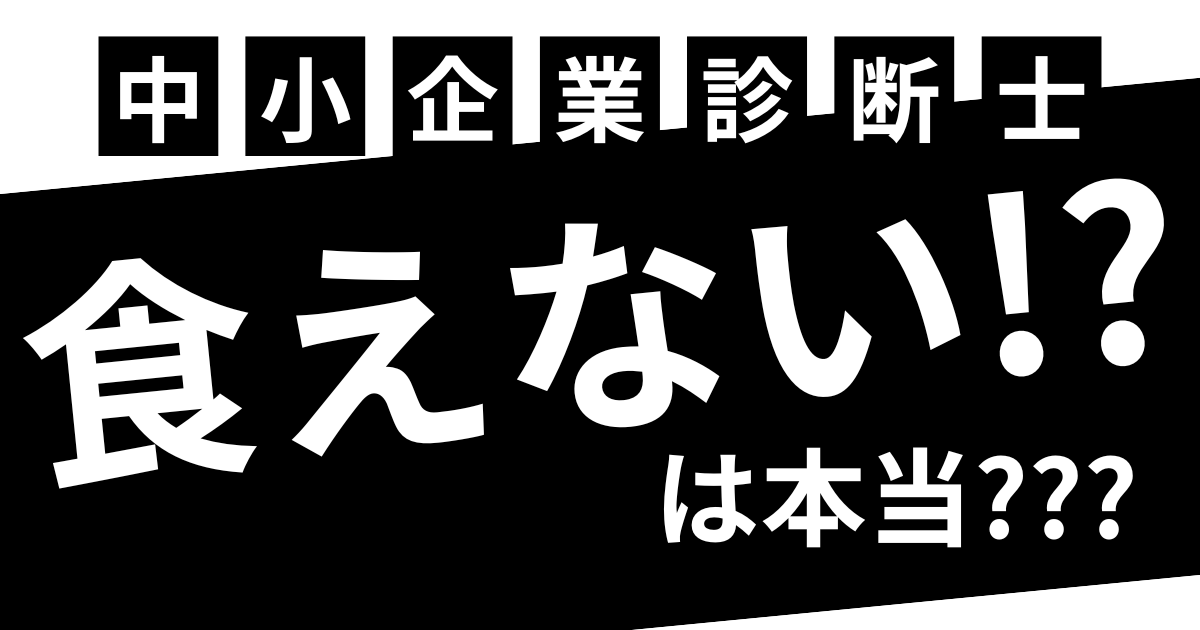
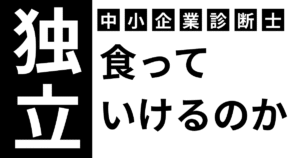

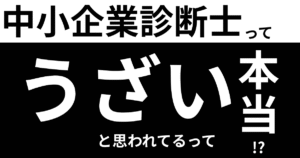
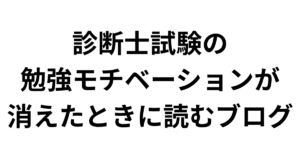
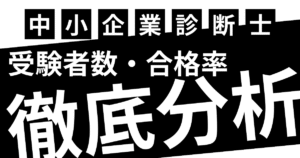
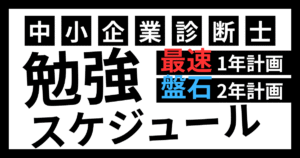

コメント