昔はできていたのに、今はできない、早起き。
誰もが一度はやってみようと思ったことがあること。早起き。
学生の時は授業が始まる関係でいくらでも早起きができていた。日中に眠たくなることは多々あったけどそれでも起きる時間は固定できていたし、授業も7時30分から受けていた。つまり、早起きして仕事するみたいなことが学生時代はすんなりできていた。
一方で社会人になってからは、早起きがしんどくなってきている。
前日の夜に飲み会があるとか、ちょっと遅くまで仕事をするとかが増えてきて早い時間に起きることができなくなってきている。
なおかつ、働き方によってはフレックスという何時に仕事を始めても良いという状況がさらに早起きする理由をなくしているように思う。
昔は自然と早起きできていたのに、今ではできない。なんでだろうと考えてみた。
早起きができないのは「始まる時間・終わる時間」が決まっていないから
早起きができない理由を学生の時と比べてみると、その理由の一つには「始まる時間・終わる時間」が決まっていないことがあると思う。
学生の頃は授業が開始される時間が決まっている。終わる時間も決まっている。部活の時間も決まっている。家に帰る時間も大体決まっている。
というように、1日の出来事の始まる時間・終わる時間が決まっているので、その中で自分のやりたいことをやりくりするようになる。
一方で、社会人になると始まる(始める)時間と終わる時間は結構自由にコントロールできる。
特に現代はフレックスタイム制の導入により、好きな時間に好きなように仕事ができる職場も増えてきている。
こうなってくると、早起きしなくても別に問題ない。なぜなら、働く時間はコントロールできるし、仕事を終える時間もコントロールできるから。
こう考えてみると、そもそも「早起き」というのは絶対にやらないといけないものではないと再認識できた。「早起き」は早起きして何かをやりたいという人が取り組めば良いもの。
まぁ自分の場合は「早起き」して有意義な時間の使い方をしたいと思っているのだけれど。
早起きを習慣化するための方法
早起きをするための方法を調べたり、本を読んだりしてざっくりまとめてみたいと思う。
肝心なのは「習慣を作り出すメカニズム」を利用するということだ。
詳しくはこの本に書いてある。
習慣は下記の3つのループで構成されているそうだ。
①きっかけ(Cue)
習慣が始まる引き金となるもの。時間、場所、感情、他人の存在、直前の行動など。
②行動(Routine)
実際に行う習慣的な行動。
③報酬(Reward)
行動の後にもたらされる満足感、快感、達成感など。脳が「この行動は価値がある」と判断する要素。
つまり、3つを意識すれば習慣になりやすいということだ。
となると、この3つを考慮した朝と夜の習慣を作り出すことができれば「始まる時間・終わる時間」が固定化されてより起きやすい状態を作り出せそうだ。
まずはその習慣の方を作ってみるところから始めたいと思う。

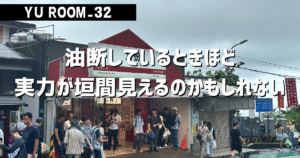
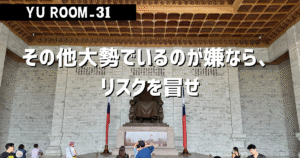
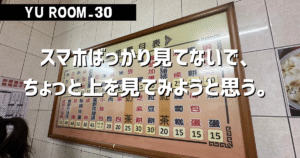
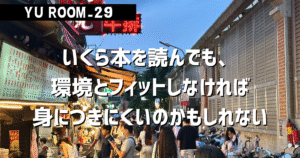
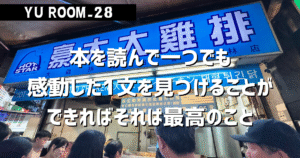
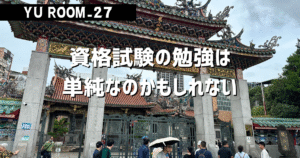
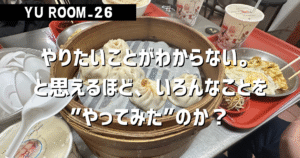
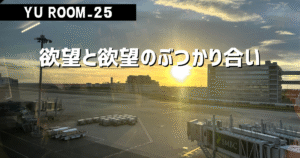
コメント