中小企業診断士試験に年齢制限はある?
中小企業診断士試験に興味を持っている人たちがまず調べることは、難易度・受験者の特徴であるケースが多いはずだ。
「興味はあるけど、自分と同じような人も受験しているのか?自分は合格できるのか?が気になる」
そんな思いに対して一つの答えをこのブログでは提供できればと思う。
結論から言えば、中小企業診断士試験には年齢制限は一切ない。高校生でも、定年退職後のシニアでも、「診断士になりたい!」という強い気持ちさえあれば受験できるし、合格もできる。
「中小企業診断士に挑戦したいけど自分には無理かもしれない、、、」と思っている人がいたらその考えは間違いだということだ。誰でも挑戦できるし、誰にでも合格のチャンスはある。これが中小企業診断士試験である。
と言いつつも、やっぱり下記のような疑問は湧いてくるはず。
実際はどの年代が多く合格しているのか?
自分と同じ世代はどのくらいいるのか?
そんな疑問を抱いた方のために、中小企業診断士試験の概略をみた後に、実際に年齢分布をデータで示していく。あなたが中小企業診断士試験に挑戦する一つの参考になれば幸いだ。
中小企業診断士試験の概略
一次試験
中小企業診断士試験において、合格の鍵を握るのはこの1次試験である。極めて重要な試験であると言って過言ではない。
その理由は明確である。1次試験の試験科目は全7科目で構成されているが、そのうちの3科目は、2次試験および口述試験においても出題対象となる。すなわち、1次試験は単なる通過点ではなく、後続する2次試験・口述試験の基盤をなす位置づけにある。
より具体的に言えば、1次試験の7科目は、2次以降にも直結する最重要3科目と、基本的には1次試験でしか使用しない4科目(ただし、稀に応用的に使われるケースもある)に分けられる。したがって、1次試験の段階で全体像を把握し、重点的に取り組むべき科目を見極めることが、合格への戦略上、不可欠である。
具体的な科目は下記のとおりである。
企業経営理論
企業経営理論は、経営戦略・組織論・マーケティングなど幅広い知識を扱う中核科目である。実務や2次試験にも直結するため、単なる暗記ではなく、知識の活用を意識した学習が重要である。
財務・会計
財務・会計は、数値分析力が問われる科目であり、資金調達や投資判断、財務諸表の読み取りを学ぶ。2次試験や実務でも重要な分析力を養う基礎となる。
運営管理
運営管理は、生産計画や在庫管理、店舗運営など、製造業・サービス業に関する実務知識を問う。2次試験の事例にも頻出で、現場感覚を活かせる重要科目である。
経済学・経済政策
経済学・経済政策は、ミクロ・マクロ経済の理論と政策を扱う。数式やグラフを用いた分析が多く、経済現象を論理的に理解する力が求められる。
経営法務
経営法務は、会社法や契約法、知的財産などを扱い、企業活動の法的リスクへの理解を深める。専門用語に慣れが必要だが、実務にも直結する知識である。
経営情報システム
経営情報システムは、IT基礎、システム開発、セキュリティ、DXなどを学ぶ科目である。経営改善に直結する内容であり、IT未経験者は早めの対策が必要である。
中小企業経営・政策
中小企業経営・政策は、中小企業の経営課題と支援策に関する知識を問う。法律や補助金制度などの理解を通じて、現場と行政の橋渡しができる実務力を養う。
二次試験
中小企業診断士の2次試験は、主に事例問題を通じて実践的な経営課題解決力を問う試験である。1次試験とは異なり、記述形式で実施される点が特徴である。
試験は全4事例で構成され、実在する企業をモデルとしたケースに対し、経営戦略の立案、課題の抽出、具体的な改善策の提案といった能力が求められる。具体的には、事例Ⅰは「組織・人事」、事例Ⅱは「マーケティング・流通」、事例Ⅲは「生産・技術」、事例Ⅳは「財務・会計」に関する問題が出題される。
解答にあたっては、1次試験で習得した知識を土台としつつ、論理的かつ実践的な思考をもとに、具体性のある提案を行うことが求められる。
口述試験
口述試験は、2次試験の筆記試験に合格した受験者が受ける最終試験であり、面接形式にて実施される。試験時間はおおむね10分程度で、試験官より2次試験で出題された事例に基づく質問が2〜3問出題される。
内容は、事例企業の課題に対する解決策や、その根拠について受験者が説明する形式が中心であり、実務的な視点から論理的かつ明確に回答することが求められる。特に、口頭でのコミュニケーション能力や、経営課題に対する提案力が評価の対象となる。
受験者は、冷静かつ簡潔に、自信を持って自身の見解を述べることが重要であり、診断士としての適性が最終的に問われる場でもある。
合格者の年齢分布をデータで解説
直近5年間の”受験者”の推移
直近5年間の中小企業診断士の受験者数を年代別に分けると下記のようになる。
| 年齢・年代別受験者数 | 2023年度(令和5年) | 2022年度(令和4年) | 2021年度(令和3年) | 2020年度(令和2年) | 2019年度(令和元年) |
| 20歳未満 | 140 | 136 | 165 | 150 | 126 |
| 20~29 | 3,463 | 3,681 | 3,851 | 3,288 | 3,149 |
| 30~39 | 7,143 | 7,103 | 7,149 | 6,124 | 6,442 |
| 40~49 | 7,551 | 7,187 | 7,111 | 5,803 | 6,321 |
| 50~59 | 5,865 | 5,118 | 4,785 | 3,665 | 3,898 |
| 60~69 | 1,667 | 1,410 | 1,290 | 1,018 | 1,090 |
| 70歳以上 | 157 | 143 | 144 | 121 | 137 |
| 合計 | 25,986 | 24,778 | 24,495 | 20,169 | 21,163 |
受験生の年代のボリュームゾーンは30代〜50代。最も受験者が多い世代は年によって異なるが、30代か40代ということになる。そして、もう一つ特徴的なのが、受験者数は年々増加傾向にあるということ。つまり、中小企業診断士はこれまで以上に人気の資格になりつつあることがわかる。
あなたと同じように中小企業診断士に興味を持って、チャレンジしようとする人はどんどん増えているということである。世の中のリスキリングブームも影響しているだろう。
直近5年間の”合格者”の推移
受験者数だけではなく、さらに気になるのは合格者数ではないだろうか。次に合格者の年齢構成を見てみる。
| 年齢・年代別合格者数 | 2023年度(令和5年) | 2022年度(令和4年) | 2021年度(令和3年) | 2020年度(令和2年) | 2019年度(令和元年) |
| 20歳未満 | 17 | 9 | 22 | 19 | 7 |
| 20~29 | 739 | 769 | 889 | 816 | 540 |
| 30~39 | 1,623 | 1,593 | 1,779 | 1,609 | 1,401 |
| 40~49 | 1,574 | 1,424 | 1,674 | 1,398 | 1,377 |
| 50~59 | 1,220 | 966 | 1,152 | 906 | 871 |
| 60~69 | 329 | 238 | 306 | 237 | 228 |
| 70歳以上 | 19 | 20 | 17 | 20 | 20 |
| 合計 | 5,521 | 5,019 | 5,839 | 5,005 | 4,444 |
合格者数の実数だけ見ても、年代別の合格率は分からないので、受験者数と合格者数を使って合格率を出してみると下記になる。
| 年齢・年代別合格率 | 2023年度(令和5年) | 2022年度(令和4年) | 2021年度(令和3年) | 2020年度(令和2年) | 2019年度(令和元年) |
| 20歳未満 | 12.14% | 6.62% | 13.33% | 12.67% | 5.56% |
| 20~29 | 21.34% | 20.89% | 23.08% | 24.82% | 17.15% |
| 30~39 | 22.72% | 22.43% | 24.88% | 26.27% | 21.75% |
| 40~49 | 20.84% | 19.81% | 23.54% | 24.09% | 21.78% |
| 50~59 | 20.80% | 18.87% | 24.08% | 24.72% | 22.34% |
| 60~69 | 19.74% | 16.88% | 23.72% | 23.28% | 20.92% |
| 70歳以上 | 12.10% | 13.99% | 11.81% | 16.53% | 14.60% |
| 合計 | 21.25% | 20.26% | 23.84% | 24.82% | 21.00% |
これをみると、年によってばらつきはあるが全体の合格率は20%前後であるといえる。高いような低いようなよく分からないと感じた方もいらっしゃると思うが、中小企業診断士試験は年に1度しか試験が実施されない。つまり、多年度受験生も一定数存在するということである。数年間勉強している人も含めてこの合格率ということは難易度はそこそこ高いと言えるだろう。
一方で40代・50代は実務経験が豊富ということもあり、中小企業診断士試験の基礎となる知識は既に持っている可能性がある。この場合は20代・30代よりもスタートダッシュは切りやすい。
年代別の合格者傾向と特徴
30代・40代での合格が多い理由
年代別に見ると、30代の合格率が高い傾向がある。そして、年齢を追うごとに合格率は若干ではあるものの下がっていく傾向があるようだ。
つまり、社会人である20代〜30代は中小企業診断士試験に対する相性がいいのかもしれない。
試験範囲が膨大で覚えなければいけない量も一定数ある。これに耐えられる体力と記憶力を持っている20代・30代は有利に試験に臨める可能性が高い。
20代・30代では仕事・私生活でイベントが盛りだくさんで、勉強時間がなかなか確保できない状況もあるかもしれない。しかし、体力と勉強を維持するモチベーションという意味でいうと、この年代ほど適している時期はないだろう。
50代・60代での合格が多い理由
一方で40代・50代は実務経験が豊富ということもあり、中小企業診断士試験の基礎となる知識は既に持っている可能性がある。この場合は20代・30代よりもスタートダッシュは切りやすいはずだ。
また、中小企業診断士試験の二次試験は記述式である。ビジネス現場での経験が豊富なほど、記述式にも対応しやすいという傾向はあるだろう。
勉強に対する体力は20代・30代ほどではないかもしれないが、長年培ってきた経験値が発揮されるのは間違いなく40代・50代だろう。
全年代で言えること
まとめると、それぞれの年代の特徴はあるものの、捉え方次第。中小企業診断士にチャレンジしようと思っているのであれば思い切って勉強してみることが良いのではないだろうか。
まとめ
中小企業診断士合格への道は、決して平坦なものではないことは間違いない。
しかし、最も重要なのは「決して諦めないこと」であるように思う。学習の過程では、必ずと言ってよいほど壁にぶつかる瞬間が訪れる。実際、私自身も何度取り組んでも理解できず、記憶に定着しない論点に何度も直面した。
それでも、学習を継続し、粘り強く取り組み続ければ、必ず理解できる瞬間がやってくる。これは断言できる事実である。これに年代は関係ない。
努力を積み重ね、あきらめずに進み続ける限り、結果は必ずあとからついてくる。
「勝つまでやる」。
この姿勢こそが、合格への最大の鍵である。失敗を恐れず、挑戦し続ける者にのみ、勝利の日は訪れる。諦めない者が、最後には勝つ。ぜひ、中小企業診断士試験に挑戦してみてほしい。
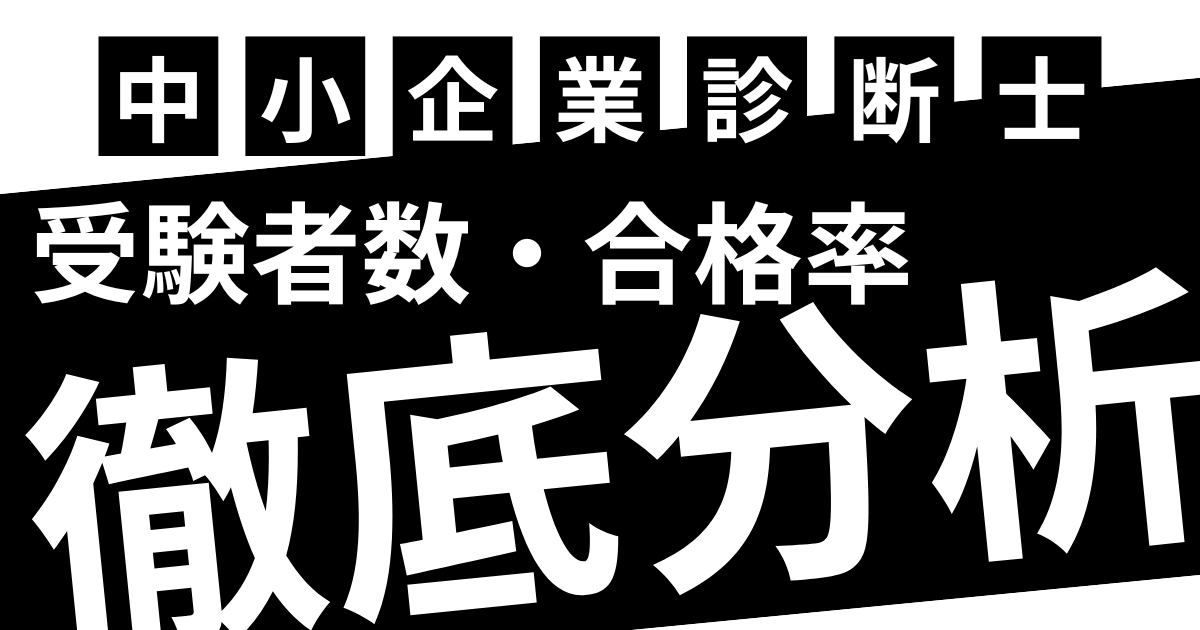
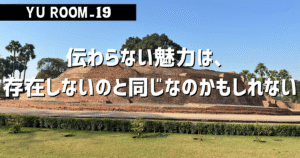
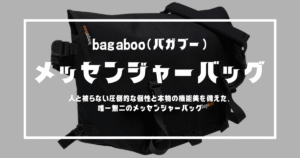
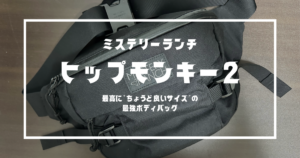

コメント