はじめに
まず、最初に、診断士の勉強でやる気が続かないのは普通だ。むしろ、モチベーションを気にせずに勉強を続け、合格を掴み取る人の方が珍しいはず。
このブログでは、中小企業診断士の勉強でモチベーションがさがる理由とその対策について解説をする。このブログでさらに意識したいのは、世の中に散らばっている”抽象的でテンプレート的な”内容はさけて、具体的な話を展開することである。
「モチベーション維持について調べてるけど、ちょっと具体性がない、テンプレート的な記事ばかりだな」と感じられていた方は是非参考にしてほしい。
そもそもモチベーションとはなんなのか?
ちょっと立ち止まって考えてみよう。モチベーションってそもそも何か?
教科書的な説明は下記のようになる。
“人が行動を起こしたり、目標に向かって努力したりする際のエネルギーや動機づけ”
ん〜。イメージしていたことがテキストになっただけでいまいち掴めない。
もう少し具体化すると、モチベーションというのは2つに分類されるそうだ。
内発的モチベーション(intrinsic motivation)
好奇心や達成感など、行動そのものが楽しい・意味があると感じることから生まれる。
例:「中小企業診断士の勉強が楽しい」「新しい知識を得るのが嬉しい」
外発的モチベーション(extrinsic motivation)
報酬、評価、昇進、周囲の期待など、外部から与えられる要因による。
例:「昇進のために資格を取りたい」「家族に褒められたい」
さて、どうだろうか。ここまでくるとモチベーションというものへの解像度が上がってくるのではないだろうか。要は、自分の内側から発生するモチベーションと外側から発生するモチベーションがあるということだ。
ということは、診断士の勉強でモチベーションが維持できない、やる気が出ない、というのは、2つのモチベーションに対して何かしらのアクションを取る必要があるということのようだ。
中小企業診断士の勉強でモチベーションが維持できない3つの理由
ここからは、中小企業診断士の勉強に関するモチベーションについて深掘りする。これからモチベーションを維持できない3つの理由を解説するが、この全てに共通する根本的な要因がある。
それは、「試験科目は合計で7科目あり、試験範囲が幅広い。つまり、時間がかかる」ことである。
中小企業診断士試験は1年に1度しか実施されないため、一度でも試験に落ちてしまうと、長期戦になることが確定する。
仮に、一次試験に落ちてしまうと次のチャレンジは1年後。一次試験に合格しても、二次試験に落ちると次のチャレンジは1年後。というように、1年に1度の試験のため一度の不合格で、合格までの期間が最低でも1年延長されることは間違いない。
そもそもの根本原因は「時間がかかりすぎること」にある。ではこの根本原因をさらに3つに分解していく。
①テキスト・問題集を解く中でどう足掻いても理解できない・忘れてしまう内容(苦手科目)が出てくる
中小企業診断士は合計で7科目に合格しなければならない。その試験範囲は幅広く、どうしても自分が苦手とする分野が出てくる。
先のほどのモチベーションでいうと、最初は中小企業診断士の知識を得ること自体が楽しかったりするのだが、勉強をすればするほど、よくわからない内容が出てくる。
これが積み重なると、中小企業診断士の勉強がどんどん楽しくなくなる。内発的モチベーションがガンガン下がる。なんなら、特定の単元のことがちょっとうざくなってくる。
私の場合は運営管理の在庫管理あたりはうざすぎて、無理矢理暗記した笑
予備校に通っていれば、勉強のカリキュラムがあり、最新の情報をもとに学習すべきポイントが理解しやすく、問題の添削や解説も質問できるけれど、独学ではそれができない。
これがどんどんモチベーションを蝕んでいく。
②できた!理解した!と思っても久しぶりに解いてみるとすっかり忘れてしまっている
中小企業診断士試験は合計7科目で構成されており、1日で全てを勉強しながら合格を目指すのは非現実的。特に日中は働いている社会人の方の受験が多い試験でもあるため、どれだけ頑張っても1日に勉強できるのは1科目から2科目くらい。
しかし、7科目を順番に学習していく中で、最初の方に学習した内容は自分でもびっくりするくらい頭から抜け落ちていることがほぼ確実に発生する。
あの時は理解したはずなのに、、、また振り出しに戻った、、、という経験を必ず経験する。
幅広い試験範囲なのだから当たり前といえば当たり前なのだが、忘れてしまっている事実に直面するたびにモチベーションは削られていく。
③私生活では中小企業診断士以外のイベントも盛りだくさんで、優先順位がつけられなくなる
中小企業診断士試験だけを勉強し続ける生活なら合格は簡単かもしれない。しかし、多くの場合私生活との両立が前提となるだろう。
友達との付き合い、彼氏彼女との付き合い、家族とのイベント、自分の趣味、仕事に関する資格や試験の勉強、などなど。上げ始めたらキリがないくらい私生活のイベントは盛り沢山のはず。
そしてその多くが、楽しいことばかりだと思う。
こうなってしまうと、勉強を継続することが難しくなり、ついつい私生活のイベントの優先順位が高くなってしまうことがある。
これ自体は全く悪いことではないのだけれど、勉強しなかった期間が長ければ長いほど勉強内容は頭から消え去っていくのもまた事実。
こうなってしまうと学習効率はどんどん落ちていき、合格までの年数が多くなり、いつの間にかモチベーションが消え去る、、、ということが起きてしまう。
モチベーションを維持する3つの方法(合格者の体験談)
モチベーションが維持できなくなる3つの理由は書いたものの、正直、あげ始めたらきりがないくらいモチベーションが維持できない、上がらない理由はある。それでも、中小企業診断士に合格したいのであれば勉強しなければいけない。
そこで、ここからは実際に中小企業診断士の勉強を経験した合格者から聞いたモチベーション維持の方法をみていく。
① 勉強の進捗を見える化する(これが1番重要)
モチベーション維持に最も効く対策はおそらくこれ。勉強の進捗を見える化して自分がちゃんと合格に近づいていることを頭で理解することである。
これ、あらゆるところで言われていることで、「うわ、でた。無味無臭なテンプレートみたいなこと言い始めた」と感じた人もいるかもしれない。ただ、これ本当に重要。ちょっと例え話をするのでもう少しだけ読んでほしい。
例えば、100時間授業を受けると合格する試験があったとする。そしてこの試験に合格したいとする。このケースでは100時間授業を受けるだけで、合格するのである。
このような状況であれば、誰もが100時間しっかり授業を受けて合格しようとするだろう。当たり前の話だ。
実はこれ、診断士の勉強にもほぼ同じことが言える。
これは、別のブログでも書こうと思うが、中小企業診断士に合格するための勉強方法は、下記の2つを実行することである。
・各科目のTACのスピード問題集を100%正解できるようにする(正解の選択肢以外もなぜ正解ではないのかを説明できるレベルにする)
・各科目の5年分の過去問を解き、100%正解できるようにする。
これができれば、1次試験はほぼ間違いなく合格できる。
つまり、合格までにやるべきことは決まっているのである。
このやるべきことをベースに中小企業診断士に合格するまでの勉強スケジュールを組み立て、目の前の1週間でどれくらい進めるのかを常に記録し続ける。
これができればモチベーションは維持できる。なぜなら、合格までにやらなければいけないことは確定しているので、それをやりきりさえすればいいからである。不合格になることを考える余地はない。ただやるだけである。
さっきあげた、100時間の授業を受ければ合格する試験と本質は同じというわけだ。
合格するまでに必要なことをスケジュールに落とし込み、それを1週間単位でどれくらい進んでいるのか記録して、見返す。これで自分が確実に合格に近づいていることがわかり、モチベーションが維持できるはずだ。
② 過去の自分の努力を振り返る
これは①ができていれば、自ずと達成できるものだ。
勉強の習慣がない人は、2、3日勉強していない日が出てくると、モチベーションが下がってくる。勉強できなかった自分に対しての自己嫌悪も始まる。
そうすると、再び机に向かって勉強することが億劫になる。これで、また数日間勉強しなくなり、結局1週間くらい勉強していないから巻き返すこともめんどくさくなるし、大変になる。
これを防ぐために、自分の勉強してきた努力を振り返ることが本当に重要だ。
2、3日勉強しなかったところで、過去の積み重ねはなくならない。過去に積み重ねた勉強の記録を見ると自然と「ちょっとサボっちゃったけど、自分、結構頑張ってるじゃん。ここでやめたらもったいない」と思える。
勉強をサボってしまったり、モチベーションが下がっている時こそ、自分の勉強の記録を見直そう。そして、確実に合格に近づいていることを頭で利用しよう。
これが、再スタートする力になる。
③ 中小企業診断士に合格したい理由を振り返る
これはサブ的なもの。正直、これでモチベーションが完全復活することはないだろう。だが、大切。
中小企業診断士に合格しようと思っていることはやりたいことがあるはずだ。
・副業を始めて収入を増やしたい
・独立したい
・企業内診断士として今の会社で活躍したい
・日本の中小企業を元気にしたい
などなど。これを思いだそう。モチベーションが下がって、勉強をしなかったら、合格が遠ざかり、やりたいことができなくなる。本当にそれでいいのか?後悔はないか?と自分に問いかける。
これをすると、モチベーションうんぬん言ってられなくなる。やるしかなくなる。
まとめ|モチベーションは消えて当然。でも、合格はその先にある。
中小企業診断士の勉強は、長期戦で、地味で、思った以上にしんどい。でも、だからこそ「やる気が出ない」と感じる瞬間があるのはむしろ普通なこと。
むしろ、「ずっとモチベーション高く頑張れてます!」って人のほうがレアキャラ。
だからこそ、進捗を記録して、見える化して、少しずつ「合格に向かって前に進んでる自分」を確認する。
2、3日サボっても、過去の自分の努力がちゃんと残ってることに気づいて、「ここでやめたらもったいない」と思えるようになる。そして、時々「なんで診断士を目指したんだっけ?」と自分に問いかける。
これらをやるだけで、モチベーションは少しずつ立て直せる。というか、無理に上げなくても、合格まで歩き続けられる自分になれるはず。
正直、全て完璧にやる必要なんてない。多少サボっても、多少ダレても、戻ってくればいいだけ。
それくらいの「ゆるさ」と「したたかさ」が、診断士の勉強には必要なんだと思う。
あなたも、ちゃんと積み重ねればちゃんと合格できる。応援しています。
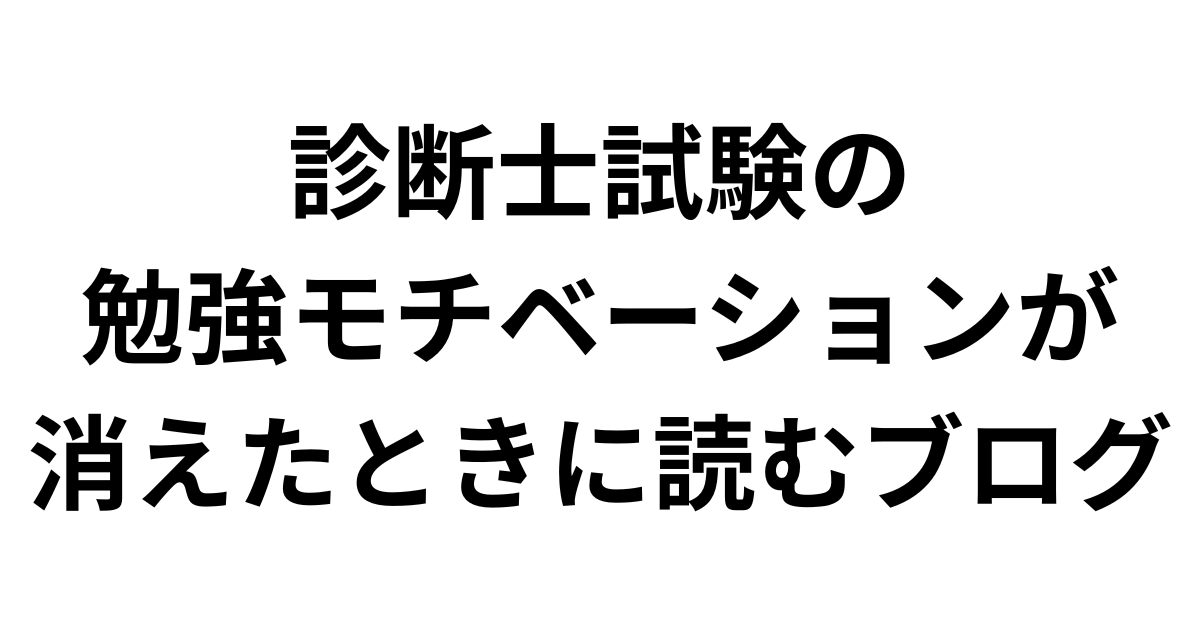
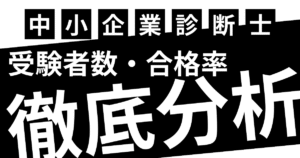
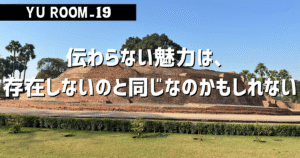
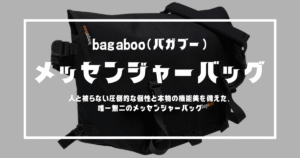
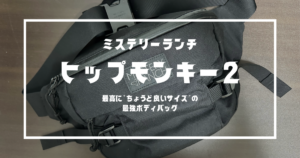

コメント